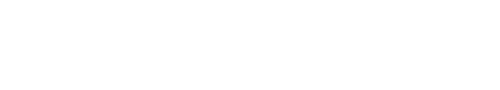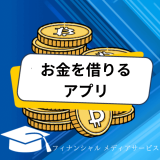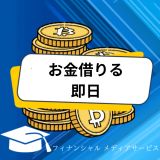クレジットとローンの違いって何?
ローンと分割払いの違いは?
このような悩みや疑問を持つ方に、この記事はおすすめです。
クレジットは、商品やサービスなどを購入したタイミングで
実際の料金支払いは行わず、
後から支払う約束のことを指しますが、
一つの例として、身近なものは、現金を持っていない時に便利なクレジットカードを指すことが多いでしょう。
高額な商品を購入する際に組むローン。
実際に、利用したことがある人は多いと思います。
ですが、それぞれの違いについて正しく理解していない人も多いです。
この記事では、「クレジット」とはどういう意味なのか、クレジットとローンの違いやクレジットを利用する際のポイントについて解説します。
クレジットとは

クレジットは、「信用」のことを指し、一般消費者のよく利用する、「クレジットカード」、他にも、各国の政府や、企業が、外貨を必要とする時に、短期の借入れの契約をする、「借款」が意味に含まれます。
現代の日本では、主に「クレジット」が指す言葉の意味は、
「クレジットカード」を意味することが一般的で、クレジットカードは、商品の購入やサービスの提供を受けるために、選択できる支払手段を指します。
この記事は、「クレジット」について、主にクレジットカードの事例を用いてご紹介していきます。
例えば、スーパーで食料品を購入する際は商品を購入するために支払い手段(現金、クレジット、電子マネー、プリペイドカード等)を選択すると思います。
クレジットカードは、現金が手元にない状態でもその場で商品を手に入れることができ、料金はクレジットカード会社が定める支払日にまとめて支払います。
クレジットカードの事例で例えると、
お金がいらないわけではなく、一旦代金をクレジットカード会社が立て替えてくれて、後日まとめて支払うという支払い方法です。
クレジットカードによる支払いは、次の3つに分けられます。
- 1回払い
- ボーナス一括払い
- 分割払い
- リボルビング払い
クレジットカードの事例:1回払い
クレジットの1回払いとは、その名の通り1回で支払いをするということです。
商品等を購入した翌月に、まとめて一括で支払う方式です。
(例)1月1日~1月31日のご利用金額を2月25日に支払う。
一番オーソドックスな支払い方法で、手数料(利息)は一切かかりません。
1万円の商品を購入した場合、翌月に1万円の支払いをするだけでOKです。
クレジットカードの事例:ボーナス一括払い
ボーナス一括払いは、夏や冬にもらえるボーナス月にまとめて支払う方式です。
ボーナス一括払いの場合も、一般的には手数料(利息)はかかりません。
尚、支払い時期は通常、夏のボーナス期間である7月か8月、冬のボーナス期間である12月か1月に利用料金をまとめて支払うことになります。
ただし、使うお店によってはボーナス一括払いができない場合もあります。
クレジットカードの事例:分割払い
分割払いは、支払い回数を指定して、複数回に分けて支払いをする方式です。
(例)1月1日~1月31日分を、2月25日と3月25日で半額ずつ支払う。
通常、2回払いまでなら手数料(利息)がかからないことが多いですが、3回以上の分割払いでは回数に応じて手数料(利息)が発生します。
分割払いでは、支払い回数を多くすれば月々の返済を少なくできます。
例えば、1万円の利用料金を10回払いにする場合、毎月1,000円ずつの支払いで済むということです。
逆に、支払い回数を少なくすれば月々の負担は多くなりますが、支払いを早く終えられます。
ただし、クレジットカードによっては分割機能がない場合もあります。
クレジットカードの事例:リボルビング払い
リボルビング払いとは、月々の支払い金額を一定額、または一定率に決めておき、その額を支払うという方式です。
例えば、毎月支払う金額を「5万円」と一定にしておけば、その間にクレジットで利用限度額の範囲内でどれだけ使おうと、月々支払いは5万円になります。
リボルビング払いの特徴として、利用金額の有無に関わらず月々の支払額が一定になるので、家計の管理に困らないです。
ただし、リボルビング払いは手数料(利息)がかかり、他の支払方式と比べても総額が高くなりますので、注意してください。
クレジットカードとローンの違い
ローンとは、銀行などの金融機関などからお金を借り、後から少しずつ支払うことを約束したものです。
例えば、車やマイホームなどの高額なお買い物をするとなると、お金を一度に用意するのが難しいでしょう。
とはいえ、クレジットの代表格、クレジットカードには、利用限度額があり、クレジットでの支払いができないケースも多いです。
そんな時に、ローンを利用すれば必要なものを必要な時に手にいれられます。
また、クレジットカードは支払いを遅らせるようなものですが、ローンは借入上限の範囲内で現金を手にすることができます。
現金を手にすることができれば、クレジットカードが使えないお店などでも支払いをすることができます。
例えば、冠婚葬祭の香典などはクレジットカードではなく現金を包みます。
ローンであれば、冠婚葬祭が続いて現金が必要になった時でも、安心です。
なお、カードローン等で借入した金銭を購入代金に該当した場合、購入した物品の所有権は完全に購入者に移転することになります。
ただし、住宅ローンの場合、ローン会社などが抵当権を持つため、支払いに滞りがあった際は購入物を取り上げられてしまう仕組みです。
クレジットカードで商品を購入した場合、品物の所有権は支払いが全て終わるまでクレジットカード会社にあります。
例えば、クレジットカードで購入したものをまだ支払いが終わっていないのに、売却してしまうことはできないということです。
クレジットカードなど、クレジットを利用する際のポイント

ここからは、私たちにとって身近なクレジットの代表格、クレジットカードを利用する際のメリットや注意点について解説していきます。
クレジットカードを利用する場合のメリット
- 手元に現金がなくてもお買い物ができる
- 利用金額に応じてポイントが貯まる
- 毎月のお金の管理がしやすい
- 付帯保険やサービスがある
クレジットを利用するメリットはたくさんあります。
まず1つ目のメリットとして挙げられるのが、「手元にお金がなくてもお買い物ができる」という点です。
クレジットを利用すれば、さまざまなシーンでキャッシュレスによるお買い物ができます。
現金を持ち歩く必要もなくなれば、もしも現金の持ち合わせがなくて支払いができない場合でも安心です。
2つ目のメリットは、「ポイントが貯まる」という点です。
一般カードの場合、クレジットの利用金額に応じて0.5%のポイントが付きます。
貯まったポイントはさまざまなお店で使えたり、好きな商品に交換することも可能です。
毎月の利用額が多ければポイントもどんどん貯まり、お得さがアップします。
例えば、毎月の固定費である家賃や公共料金、スマホ料金などをクレジット払いにするだけでも、年間を通して多くのポイントをゲットできます。
3つ目のメリットは、「毎月のお金の管理がしやすい」という点です。
クレジットカードを使った支払いは、利用明細が記載されるので、家計簿の作成が不要です。
1ヶ月の利用金額がまとめて表示されるので、支出の管理がしやすく、上手く活用すれば節約もできるでしょう。
4つ目のメリットは、「付帯保険やサービスがある」点です。
クレジットカードには、旅行傷害保険やお買い物安心保険などの各種保険が付帯されているカードが多いです。
旅行傷害保険の場合、旅行先でケガや疾病にかかってしまった場合でも補償してくれます。
出発前に手続きが必要なケースもありますが、クレジットを利用するだけでさまざまなリスクにも備えられるのは大きなメリットだと言えるでしょう。
クレジットカードを利用する場合の注意点
- 支払い期限を守る
- 利用可能枠以上は使えない
- カード紛失や盗難のリスクがある
クレジットカードは現金を持たなくてもさまざまな支払いができる便利な方式ですが、決して利用料金を支払わずに済む魔法のカードというわけではありません。
毎月の利用料金は、まとめて翌月に口座から引き落とされます。
口座の残高が不足して支払いができないと、カードが利用停止になったり、延滞金などを請求されてしまう場合もあります。
クレジットカードの利用履歴に傷が付き、新たにクレジットカードを作ったり、ローンの審査に通りにくくなってしまうリスクもあるので注意してください。
また、クレジットカードには利用可能枠がそれぞれ設定されています。
利用可能額はクレジットカードの種類や利用者のステータスによっても人それぞれ変わります。
利用可能枠以上の支払いはできませんので、注意してください。
他にも、クレジットカードが盗難・紛失などのトラブルが原因で、個人情報が漏えいしてしまったり、不正利用のリスクもあります。
最近では、カード券面にカード番号やセキュリティコードが記載されていないナンバーレスカードも増えてきています。
クレジットカードでの決済を頻繁に利用するなら、セキュリティやサポートが充実しているクレジットカードを選ぶようにしましょう。
まとめ

クレジットとローンの違いを理解できたでしょうか?
簡潔にまとめると、それぞれの違いは以下の通りです。
- クレジット:商品やサービスの代金を立て替えるサービス※詳細には、各国の政府や、企業が、外貨を必要とする時に、短期の借入れの契約をする、「借款」が意味に含まれる。
- ローン:お金を融資するサービス
クレジットとローンそれぞれにメリットとデメリットがあります。
分割払いを正しく理解して、欲しいものを手に入れましょう。